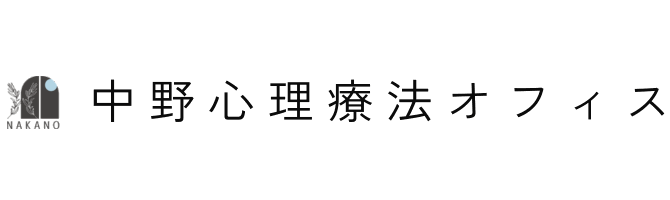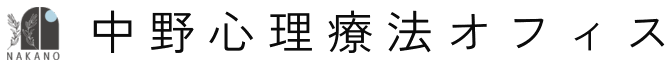先日、蜷川実花さんが監督の『ダイナー』という映画を見てきました。殺し屋のための食堂<ダイナー>で働くこととなった女性の物語で、原作の小説は残酷描写が目立つヘビーな作品でしたが、映画は蜷川実花さんらしい華やかな色彩と見せ場にあふれた作品となっていました。
映画では主人公であるカナコの過去について詳しく描写しており、幼いころから誰も信じられないまま、孤独に、受動的に生きてきた彼女が、<ダイナー>での体験を経て自分のために主体的に生きることが出来るようになっていく姿に物語の軸を置いていることが伝わってきました。
*
神話学者であるジョゼフ・キャンベルは、世界の神話や英雄譚には共通してみられる物語の構造があると指摘しています。それは「分離-通過儀礼(イニシエーション)-帰還」というもので、つまり、主人公が日常から離れた異世界にいき、そこで何らかの通過儀礼を体験し、そして成長した姿で再び元の世界にもどる、という流れです。この構造は現代の物語作成においても踏襲されることが多く、有名なところでは映画『スターウォーズ』は監督のスピルバーグが意識的にこの構造を取り入れたと言われています。
また、ジョゼフ・キャンベルは、主人公が秩序ある日常から分離して向かう先は、生と死が混じり合う混沌とした異世界であるとも述べています。生と死は人が変化すること―古い自分が死に、新しい自分が生れるーのメタファーなのでしょう。
映画『ダイナー』も、物語の展開をみるとこの「分離-通過儀礼-帰還」を辿っていると言えそうです。主人公のカナコは「日常」から離れて、殺し屋のための食堂という異世界へと入り、その生と死が隣り合わせの世界で、時に迷い、時に驚き、時に怒り、時に闘い、時に慈しむといったさまざまな体験をします。それは痛みであり混沌でもあるのですが、<ダイナー>に来る前は死んでいるかのように生きていた彼女が、鮮烈な情緒を通して自分を取り戻し元の世界に戻っていく姿は、生き生きとした生命力に満ちています。
*
心理療法もまた、この「分離-通過儀礼-帰還」という構造を有してる、と例えられることがあります。
心理療法全体は長い道のりであり、映画や神話のように短い時間で終わるものでもありません。しかし、日常から分離した面接室という空間で、 日常のモラルや合理性といった秩序に縛られず、自身の混沌とした心をそのままに体験する点、また、そういった過程を通して、時に痛みを伴いつつも以前とは異なる自分になっていく点は確かに共通しているのでしょう。
そう考えると、心理療法に来るクライエントさんは皆、ある神話(人生)において大きな冒険を成し遂げようとしている主人公である、そんな風に言えるのかもしれません。
【参考】
・『千の顔をもつ英雄<上><下>』ジョゼフ・キャンベル(ハヤカワ・ノンフィクション文庫)